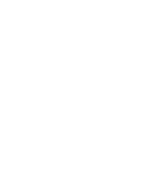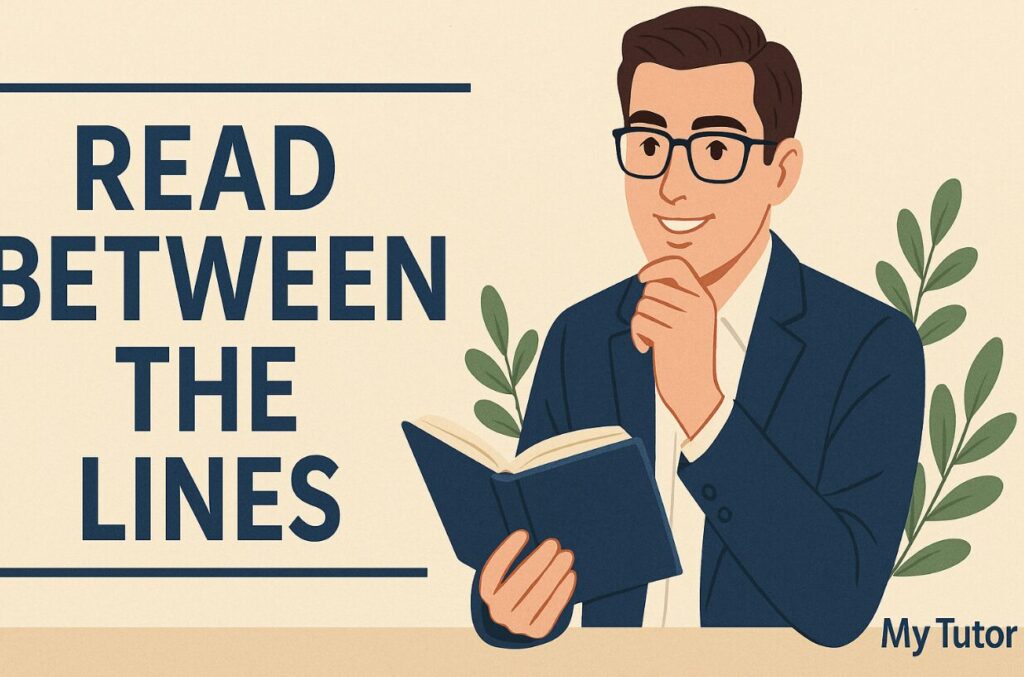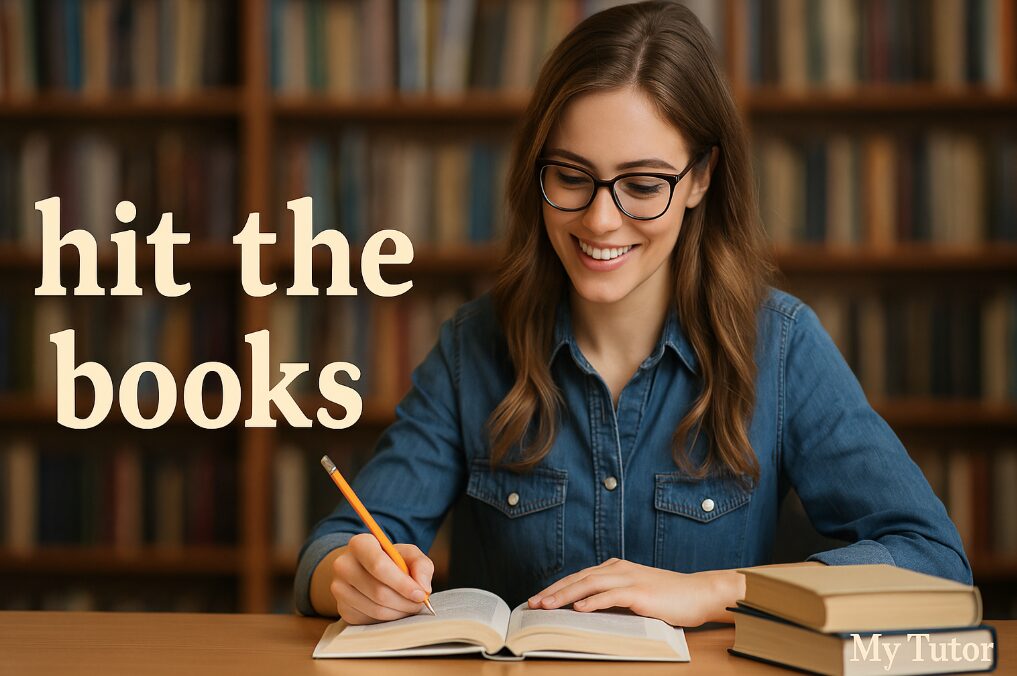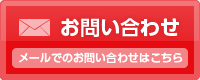🌾 今回のイディオム
“the last straw”
この表現は英語で非常によく使われるイディオムの一つで、「我慢の限界」「もうこれ以上無理」という意味を表します。
直訳すると「最後のわら」ですが、実際には「(積み重なったストレスや不満の中で)最後に決定的だった出来事」を指します。
💡 どんな意味?
“the last straw” は、「限界を超える原因になった出来事」「もう我慢できなくなった最後の一撃」という意味です。
日本語では「堪忍袋の緒が切れる」「もう我慢の限界」といった感覚に近いです。
🌱 語源について
このイディオムは、有名なことわざ
“It was the last straw that broke the camel’s back.”
(ラクダの背中を折ったのは、最後の一本のわらだった)
から生まれました。
つまり、少しずつ重なっていた負担が、最後の小さな出来事で限界を超えてしまう、という意味です。
🗣 使い方をチェック!(例文3つ)
1️⃣ After months of stress at work, my boss yelling at me was the last straw.
(何か月も職場のストレスが続いていたけど、上司に怒鳴られたのが限界だった。)
2️⃣ When he forgot my birthday again, it was the last straw for me.
(彼がまた私の誕生日を忘れたとき、さすがにもう我慢できなかった。)
3️⃣ The broken air conditioner in the middle of summer was the last straw.
(真夏にエアコンが壊れたのが、まさに最後の一撃だった。)
🔍 ポイント解説
- 通常は “That was the last straw.” や “It was the last straw for me.” のように使います。
- 感情的な限界を表すときに便利で、怒り・悲しみ・失望など幅広く使えます。
- 似た意味の “I’ve had enough.”(もううんざりだ)とセットで覚えると自然です。
🌈 似たような表現
- I’ve had it.(もう我慢できない)
- That’s the final blow.(とどめの一撃だ)
- I’m fed up.(もううんざり)
“the last straw” は、小さなことでも積み重なって爆発してしまう「人間らしい限界」を表すイディオムです。
怒りやストレスを表すときに使えば、自然でリアルな英語表現になります。
今日からあなたも、「That was the last straw!」で感情を上手に伝えてみましょう。