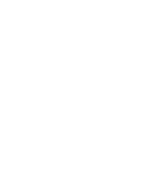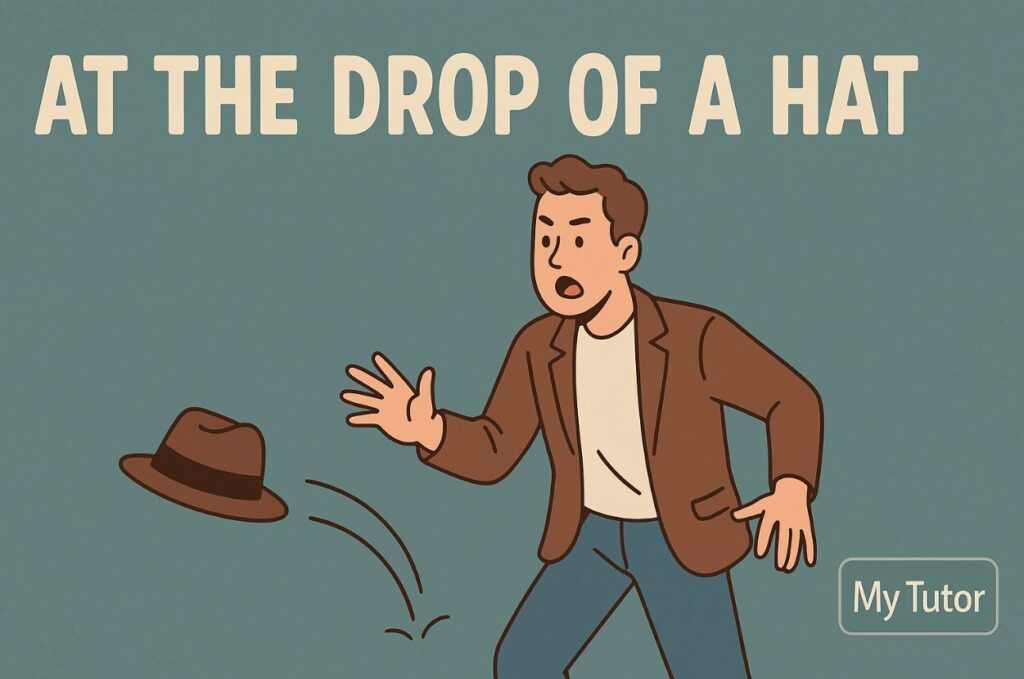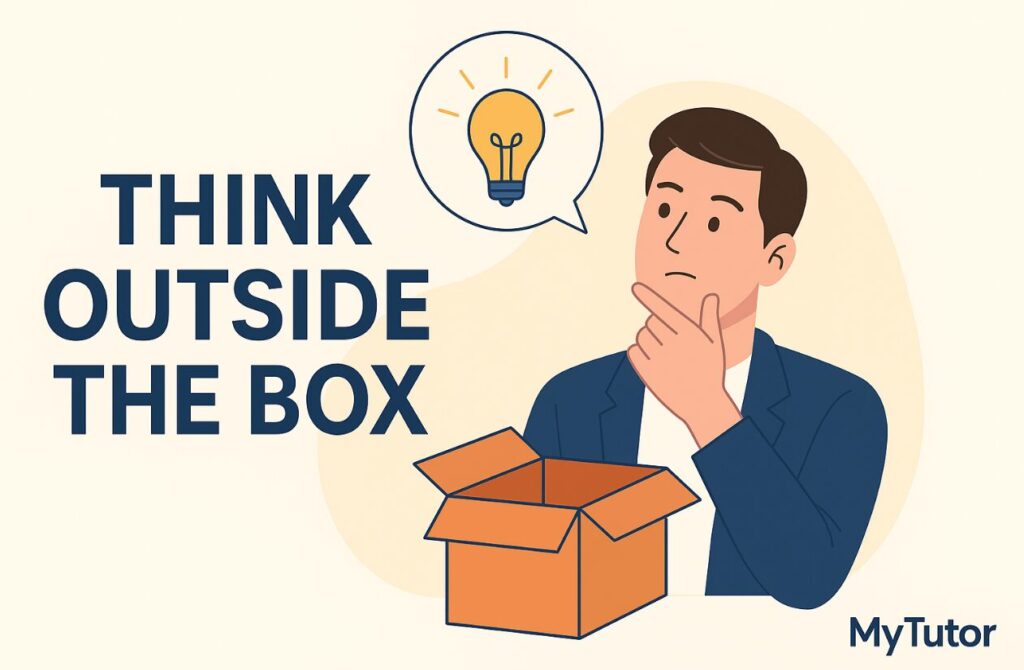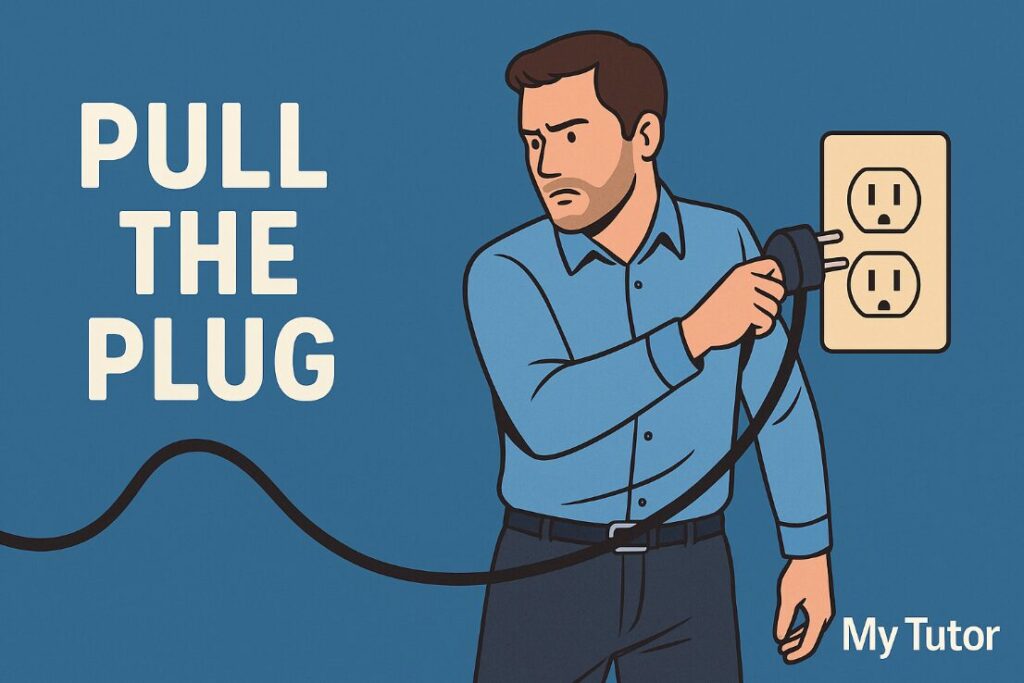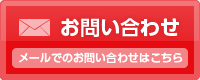🗳️ 今回のイディオム
A landslide victory
直訳すると「山崩れ(地滑り)的な勝利」。つまり、対戦相手に圧倒的な差をつけて勝つ**「圧勝」や「大勝利」**を意味します。選挙の開票速報などで、グラフの片方がぐんぐんと伸び、相手を飲み込んでしまうようなイメージですね。
⛰️ 語源について
1800年代の政治の世界で使われ始めたと言われています。山の上から大量の土砂や岩が崩れ落ちる「landslide(山崩れ)」は、誰も止めることができません。その圧倒的な破壊力とスピードを、**「誰にも止められないほどの大量得票」**に例えたのが始まりです。
💬 使い方をチェック!
- The opposition party won a landslide victory in the general election. (野党が総選挙で圧勝を収めた。)
- After their incredible performance, the team celebrated a landslide victory. (素晴らしいパフォーマンスの後、チームは圧勝を祝った。)
- Most pundits predicted a landslide victory for the incumbent. (ほとんどの専門家が、現職の圧勝を予想していた。)
💡 ポイント解説
この表現は選挙だけでなく、スポーツやビジネスのコンペなど、**「点数や票に大きな開きがある勝利」**であれば幅広く使えます。逆に、接戦(close race)の末に勝った場合には使えないので注意しましょう。
🔄 似たような表現
- A blowout: (タイヤの破裂から転じて)ボロ勝ち、大差の勝利。
- A sweep: (ほうきで掃き出すように)全勝、完勝。
- Win by a mile: (1マイルもの差をつけて)大差で勝つ。
選挙シーズンはもちろん、ビジネスシーンでの競合プレゼンに勝った時など、自信を持って「It was a landslide victory!」と使ってみてくださいね。あなたの英語の語彙力も、地滑り的な勢いで伸びていくはずです!