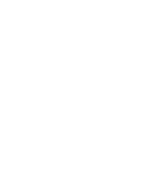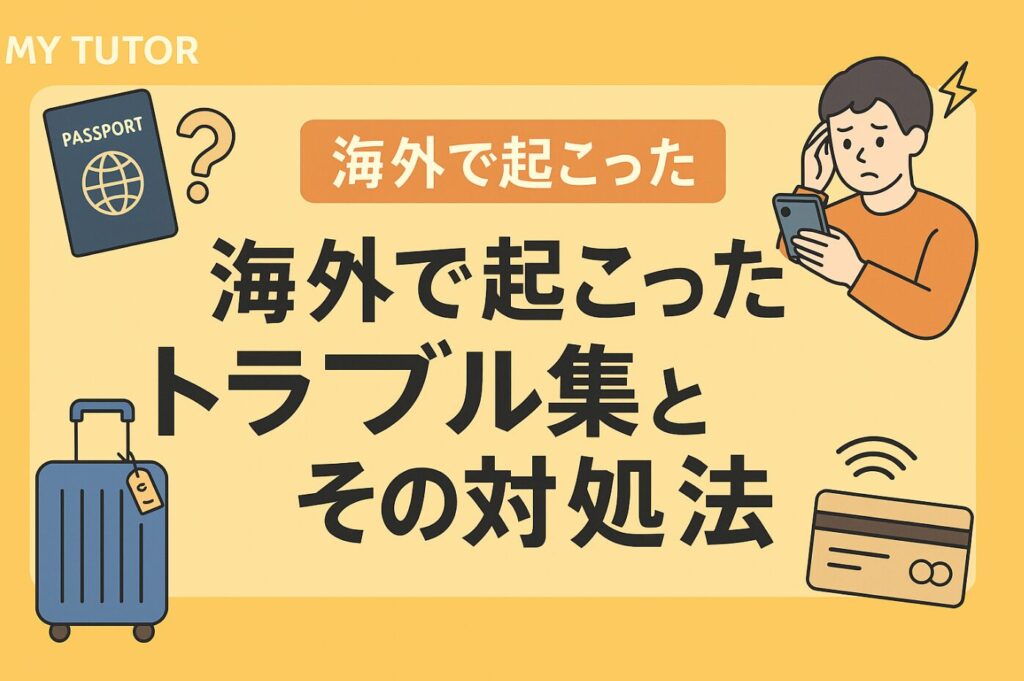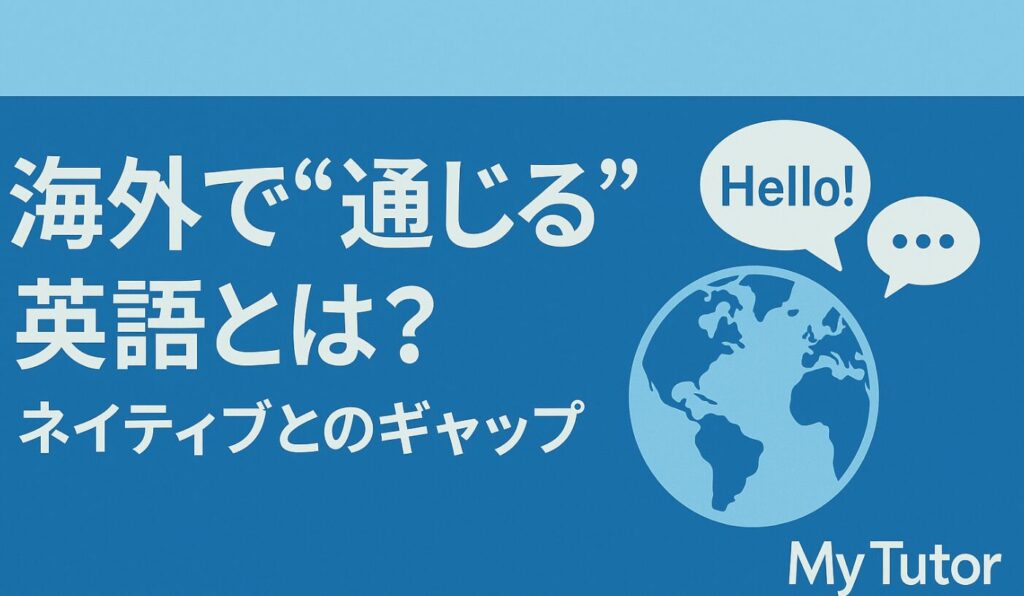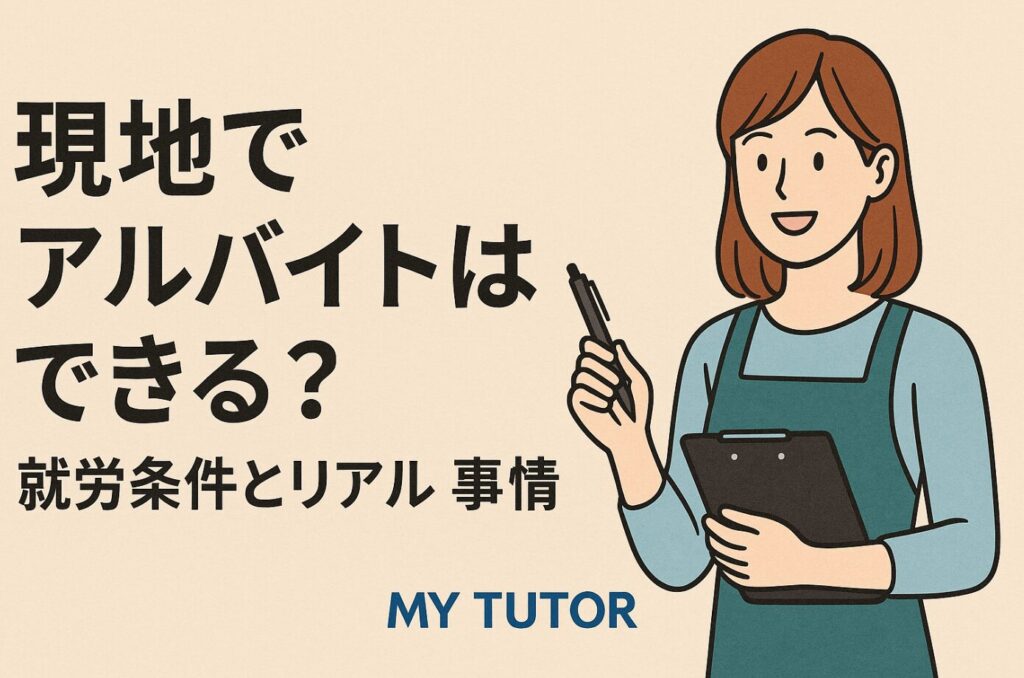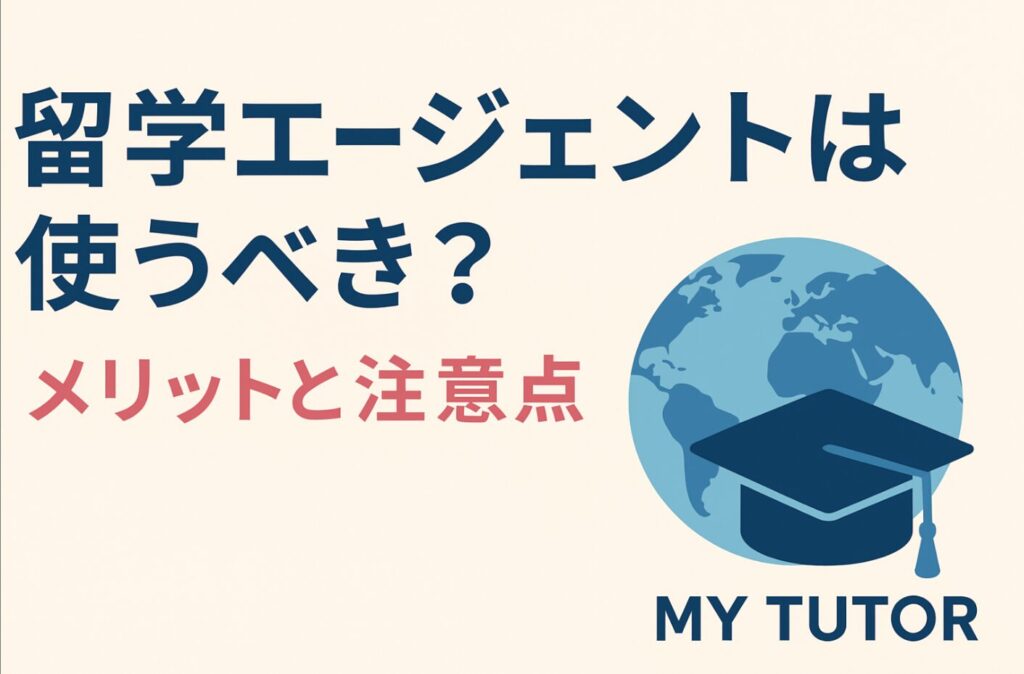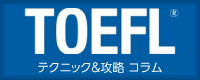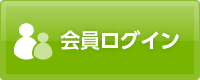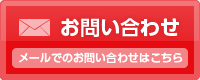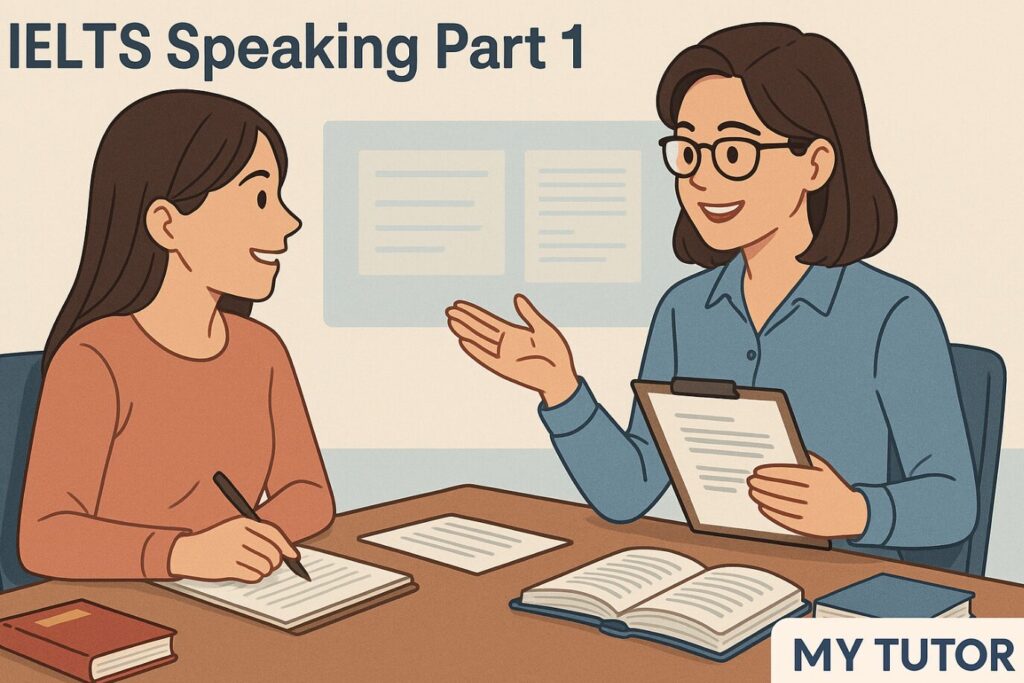
【Part 1の定番質問&答え方テンプレート】
IELTSスピーキングPart 1は、面接官との軽い会話から始まります。トピックは「趣味」「仕事」「学校生活」「家族」「休日」など日常的なものが多く、形式に慣れておけば高得点が狙えます。
このコラムでは、Part 1によく出る質問のタイプと、それに対する答え方の「テンプレート」をご紹介します!
🎯Part 1の特徴とは?
- 時間:4~5分
- 質問数:だいたい3つのトピック × 各3〜4問
- テーマ:日常生活や習慣に関すること
- 目的:リラックスさせて、受験者の基本的な英語力をチェックすること
📝よく出る質問タイプとテンプレート例
①「趣味・好きなこと」
質問例:
What do you like to do in your free time?
テンプレート:
In my free time, I enjoy [趣味]. It helps me [理由]. For example, [具体的な活動や場面] makes me feel [感情].
例文:
In my free time, I enjoy reading novels. It helps me relax and escape from daily stress. For example, I usually read in bed before going to sleep.
②「仕事・学校について」
質問例:
What subjects do you enjoy at school?
What do you do for a living?
テンプレート:
I’m currently [学生 or 職業]. I like [科目や仕事の内容] because [理由]. I find it [形容詞], and I’d like to [将来の展望].
例文:
I’m currently a university student majoring in economics. I like studying how markets work because it’s very practical. I’d like to work in finance in the future.
③「家・地域について」
質問例:
Can you describe your hometown?
What kind of house do you live in?
テンプレート:
I live in [場所]. It’s a [形容詞] area with [特徴]. I like it because [理由]. One of the best things is [良い点].
例文:
I live in a small city near Tokyo. It’s a quiet area with lots of nature. I like it because it’s peaceful and not too crowded. One of the best things is the local food.
💡答えるときのポイント
- Yes/Noだけで終わらない!
→ 必ず1~2文で理由や具体例を加える - 緊張しても笑顔を忘れずに!
→ 面接官とのアイコンタクトと自然な声で - 1文目:結論 → 2文目以降:理由や例でサポート
→ 「PREP法(Point-Reason-Example-Point)」が使いやすい
🗣️練習のコツ
- 自分の答えを録音し、テンプレートに沿って修正
- 同じ質問に対して複数のバリエーションを考える
- 友達や先生と模擬練習を行う
✅まとめ
Part 1は「慣れ」が命。聞かれる内容はある程度決まっているので、答えの「型」を覚えておくことで安心して対応できます。
テンプレートをうまく活用して、自分らしさを表現しながら、自然な英語で話す練習を重ねていきましょう!